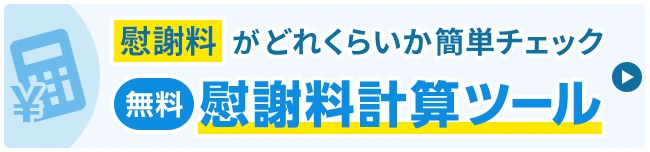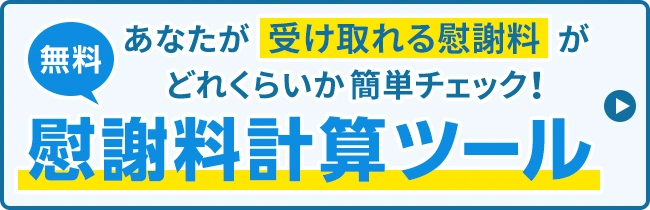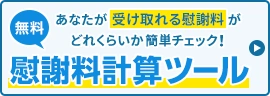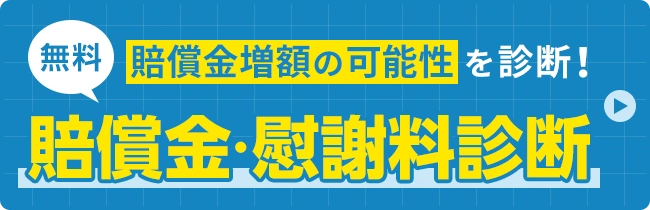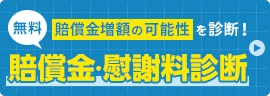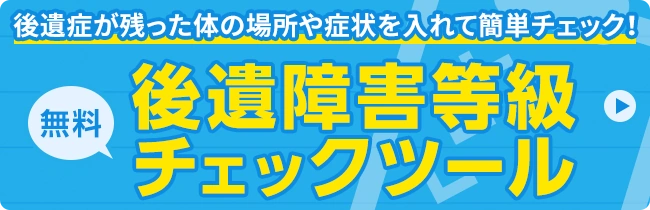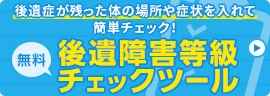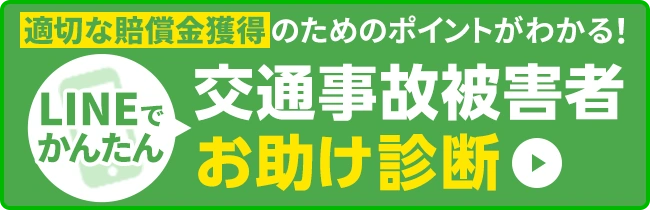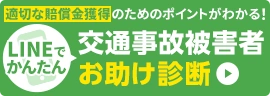交通事故で労災保険を使うには
交通事故で労災保険を使えるケース
労働者災害補償保険(労災保険)は、業務中または通勤中の労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
そのため、下記の場合には労災保険を使って診療を受けられます。
- 業務中に交通事故にあった
- 通勤途中に交通事故にあった
なお、労災給付を受けられる場合、健康保険は使えません(健康保険法第55条1項)。
健康保険を使わないと診療にかかった費用は受診者の全額負担となってしまうため、業務中や通勤中に交通事故にあって診療を受ける際には、忘れずに「労災保険を使用する」と伝えましょう。
交通事故で労災保険を使うための手続
業務中や通勤途中に交通事故にあったときは、警察や会社に連絡したうえで、労災保険を使う手続を進めましょう。
手続は、大まかに以下の手順で行います。
- 病院で診察を受ける
- 「第三者行為災害届」を提出する
- 「給付請求書」を提出する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①病院で診察を受ける
まずは、事故によるケガであることを証明するためにも、できるだけ早めに病院を受診しましょう。
このとき、受診する病院が「労災指定病院」かどうかによって、手続の方法が少し異なります。
労災指定病院の場合
労災指定病院で診察を受ける場合は、診察を受ける際に労災保険を使用したい旨を申し出ます。
その後、療養を受けている労災指定病院等に下記の書類を提出すれば、診療費の窓口負担はありません。
- 【病院への提出書類】
-
業務中の交通事故の場合:「療養補償給付たる療養の給付請求書」
通勤中の交通事故の場合:「療養給付たる療養の給付請求書」※院外の調剤薬局で薬の処方を受ける場合、病院に提出する以外に、別途療養の給付(費用)請求書が必要となりますので、請求書は2通準備してください。
労災指定病院以外の場合
労災指定病院以外の病院で診療を受ける場合は、受診する病院に下記の書類を提出し、診療内容を記載してもらいます。
- 【病院への提出書類】
-
業務中の交通事故の場合:「療養補償給付たる療養の給付請求書」
通勤中の交通事故の場合:「療養給付たる療養の給付請求書」
このとき、診療費は一時的にご自身で全額立て替える必要があります。
後日、これらの書類に診療費の領収書を添付し、労働基準監督署に提出すれば、診療費の払戻しを受けることができます。
②「第三者行為災害届」を提出する
加害者(第三者)がいて損害賠償を受けることができる労災事故を「第三者行為災害」といい、交通事故もこれにあたります。
この場合、労災給付の請求書の提出と同時または提出後速やかに、第三者災害である旨を報告する「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
「第三者行為災害届」を提出する際は、以下の書類を添付する必要があります。
- 【第三者行為災害届の必要書類】
-
- 念書(兼同意書)
- 事故証明書
- 示談書の写し(示談が成立している場合)
- 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書の写し(仮渡金または保険金の支払いを受けている場合)
- 死亡診断書の写し(被害者が死亡した場合)
- 戸籍謄本の写し(被害者が死亡した場合)
③「給付請求書」を提出する
労災保険からは、治療費や入院費などの療養(補償)給付以外にも、給付を受けられる場合もあります。
この場合は、給付の種別に対応した給付請求書と必要書類を、所轄の労働基準監督署長に対して提出します。
給付請求書の書式等は下記URLよりダウンロードできます。
交通事故における労災保険の給付内容
交通事故における労災給付には下記のようなものがあります。
| 給付の種類 | 給付されるもの |
|---|---|
| 療養補償給付 (療養給付) |
通常療養のために必要な治療費、入院料、移送費など |
| 休業補償給付 (休業給付) |
事故前の平均賃金の60%に相当する金額 |
| 障害補償給付 (障害給付) |
障害の程度に応じた年金または一時金 |
| 遺族補償給付 (遺族給付) |
受給資格を満たす遺族の方に対する年金または一時金 |
| 葬祭料 (葬祭給付) |
亡くなられた方の1日あたりの賃金に基づいた金額 |
| 傷病補償年金 (傷病年金) |
障害の程度に応じた年金 |
| 介護給付 (介護給付) |
介護の状況に応じた介護費用(上限額あり) |
※()内は通勤中の交通事故の場合の給付。それぞれの給付内容は対応する業務中の交通事故の場合の給付の内容に相当します。
それぞれの対象となるケースと給付内容を詳しく解説します。
療養補償給付(療養給付)
- 【対象となるケース】
-
業務上・通勤中のケガで療養が必要な場合
療養補償給付には、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれます。
療養補償給付を受けることで、傷病が治ゆ(症状固定)するまでの間、原則として、労災指定病院で自己負担なく治療が受けられます。
休業補償給付(休業給付)
- 【対象となるケース】
-
業務上・通勤中のケガや病気で4日以上仕事を休むケースで、賃金が受けられない・減額される場合
休業4日目から、事故前における被害者の平均賃金の60%に相当する金額が支払われます。
障害補償給付(障害給付)
- 【対象となるケース】
-
業務上・通勤中のケガや病気が治ゆ(症状固定)したあと障害が残った場合
その障害の程度(障害等級)に応じて、障害補償年金もしくは障害補償一時金が支給されます。
障害補償年金
等級が1級から7級の場合です。
毎年偶数月に、その前2ヵ月分の金額が支給されます。
| 障害等級 | 障害補償年金 (障害年金) |
|---|---|
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
※給付基礎日額=被害者の事故前の平均賃金に相当する額
障害補償年金
等級が8級から14級の場合です。支給は一度のみです。
| 障害等級 | 障害補償年金 (障害年金) |
|---|---|
| 第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
| 第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
| 第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
| 第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
| 第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
| 第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
| 第14級 | 給付基礎日額の56日分 |
※給付基礎日額=事故前の被害者の平均賃金に相当する額
遺族補償給付(遺族給付)
- 【対象となるケース】
-
業務上・通勤中の事故が原因で死亡した場合
受給資格を満たす遺族に対して、遺族補償年金(遺族年金)もしくは遺族補償一時金(遺族一時金)が支給されます。
<受給資格>
- 被害者が死亡した当時「その収入によって生計を維持していた」こと
- 被害者の配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄妹姉妹であること
- 年齢要件もしくは障害の状態を満たしていること(妻以外)
遺族補償年金(遺族年金)
受給資格者のうち最先順位の受給権者(配偶者>子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹の順)に支給されます。
受給権者が2人以上のときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
| 遺族の数 | 額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55才以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は175日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
遺族補償一時金(遺族一時金)
下記のいずれかの場合に支給されます。
- 被害者の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき(給付基礎日額の1,000日分)
- 受給資格のある者がすべて失権した場合で、それまでに支給された遺族特別年金および遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき(その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額)
葬祭料(葬祭給付)
- 【対象となるケース】
-
業務上・通勤中の事故が原因で死亡した場合
葬儀を行った方に支給されるお金です。
金額は下記のいずれか高いほうとなります。
- 3万5000円+事故前における被害者の平均賃金の30日分
- 事故前における被害者の平均賃金の60日分
傷病補償年金(傷病年金)
- 【対象となるケース】
-
療養開始後1年6ヵ月経過してもケガや病気が治ゆせず、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合
金額は傷病等級によって変わります。
| 傷病等級 | 額 |
|---|---|
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
※給付基礎日額=被害者の事故前の平均賃金に相当する額
介護給付(介護給付)
- 【対象となるケース】
-
障害補償年金または傷病補償年金を受けている方で、常時介護・随時介護を受けている場合
常時介護の場合は月額10万4,590円、随時介護の場合は月額52,300円を上限として支給されます。
交通事故で労災保険を使用するメリット・デメリット
ここで、交通事故で労災保険を使用するメリットとデメリットを知っておきましょう。
労災保険を使用する主なメリット
交通事故の被害にあったとき、労災保険を使用する主なメリットは以下の3つです。
- 特別支給金を受け取れる
- 治療費の窓口負担がない
- 過失割合に関係なく補償を受けられる
①特別支給金を受け取れる
労災保険には、上記でご紹介した各種補償給付に上乗せする形で「特別支給金」が給付されます。
特別支給金の一覧は以下のとおりです。
| 特別支給金 | 特別支給金の内容 |
|---|---|
| 休業特別支給金 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%に相当する額 |
| 傷病特別支給金 | 傷病等級に応じた以下の額の一時金
|
| 傷病特別年金 | 傷病等級に応じた以下の額の年金
|
| 障害特別支給金 | 障害等級に応じて、342万円(第1級)~8万円(第14級)の一時金が支給される |
| 障害特別年金 | 障害等級に応じて、算定基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)の年金 |
| 障害特別一時金 | 障害等級に応じて、算定基礎日額の503日分(第8級)~56日分(第14級)の一時金 |
| 遺族特別支給金 | 300万円の一時金(遺族特別支給金を受けることができる遺族が2人以上の場合は、300万円をその人数で割った額) |
| 遺族特別年金 | 遺族の人数などに応じて、算定基礎日額の153日分~245日分の年金 |
| 遺族特別一時金 | 下記いずれかの額の一時金
|
※算定基礎日額:事故前1年間の特別給与(3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与などの賃金)の総額を算定基礎年額とし、これを365日で割った額
②治療費の窓口負担がない
労災保険を使用し、労災指定の病院で診察や治療などを受けた場合、受診者には窓口負担がありません。
③過失割合に関係なく補償を受けられる
任意保険や自賠責保険に損害賠償請求する場合、被害者側に過失があるとその過失割合に応じて受け取れる金額が減額されます(過失相殺)。
しかし、労災保険の給付には過失相殺の概念がないため、たとえ被害者側に過失があったとしても、給付額が減額されることはありません。
労災保険を使用するデメリット
交通事故被害者の方が労災保険を使用する際、金銭面におけるデメリットは特にありません。
ただし、下記のような点に注意が必要です。
- 標準治療しか補償されない
- 申請手続が発生する
- 会社との関係が悪くなる可能性がある
標準治療しか補償されない
労災保険で補償されるのは標準治療の範囲のみであり、差額ベッド代などの入院雑費などは自己負担となることがあります。
また、自由診療との併用ができないため、労災保険の適用外となる治療を受けたい場合には、かかった費用の全額を支払わなければいけません。
申請手続が発生する
労災保険を利用する場合、申請手続が必要です。
申請手続を行うにあたっては、それぞれの給付金に応じた必要書類を用意しなければならず、手間がかかります。また、正しい手順を守らなかった場合、一時的に立て替えが発生することになりますので、注意が必要です。
会社に嫌がられる可能性がある
従業員が労災保険を利用した場合、業務中の事故の場合は会社が負担する保険料が増加してしまう可能性がある、会社の担当者が必要書類の作成に時間を取られる、という理由で嫌がられる場合があります。
労災保険と任意保険(自賠責保険)
通勤中や仕事中に交通事故にあった被害者の方は、労災保険からの補償に加えて、加害者側の任意保険(もしくは自賠責保険)からの賠償金も受け取ることができます。
労災保険と任意保険(自賠責保険)のどちらが優先か
労災保険と任意保険(自賠責保険)のどちらから先に支払いを受けるかについては、被害者の方が自由に選べます。
ただし、状況により、「労災保険を先行させたほうがよいケース」もしくは「任意保険(自賠責保険)を先行させたほうがよいケース」があります。
労災保険を先行させたほうがよいケース
- 被害者の過失割合が大きいとき
- 加害者が任意保険に加入していないとき
- 治療が長引きそうなとき
任意保険(自賠責保険)を先行させたほうがよいケース
- 早く任意保険会社から後遺障害慰謝料を受け取りたいとき
なお、厚生労働省からは「原則として自賠責保険等の支払を労災保険給付に先行させる(自賠先行)」との通達が出ていますが、特に強制力はありません。
二重取りはできない
労災保険と任意保険(自賠責保険)の両方に補償を請求すること自体は可能です。
しかし、同じ項目について「実際の損害よりも多く補償を受け取ること」、いわゆる「二重取り」をすることはできません。
たとえば、両方からそれぞれかかった治療費の100%金額を受け取ることはできないということです。
二重に請求した場合には、労災保険と自動車保険の間で支給調整が行われます。
| 労災保険と任意保険(自賠責保険)で重複する補償の一覧 | ||
|---|---|---|
| 補償の内容 | 労災保険 | 任意保険 (自賠責保険) |
| 診療にかかった費用 | 療養補償給付 | 治療関係費 |
| 仕事ができなかったことにより減った収入の補償 | 休業補償給付 | 休業損害 |
| 後遺症があるために失った、将来得られるはずだった利益の補償 | 障害補償給付 | 後遺障害逸失利益 |
| 被害者が亡くなったことにより失った、将来得られるはずだった利益の補償 | 遺族補償給付 | 死亡逸失利益 |
| 葬儀にかかった費用 | 葬祭給付(葬祭料) | 葬儀費用 |
| 介護にかかる費用 | 介護補償等給付 | 将来介護費 |
労災保険と任意保険の両方に請求するべき理由
もし、労災保険と任意保険(自賠責保険)の一方にしか補償を請求しなかった場合、十分な補償が受け取れないため、注意が必要です。
なぜなら、労災保険からしか受け取れない補償と、任意保険(もしくは自賠責保険)からしか受け取れない補償があるからです。
労災保険のみの補償
- 休業特別支給金
- 障害特別支給金
- 遺族特別支給金
- 傷病特別支給金
- 傷病特別年金
など
任意保険(自賠責保険)のみの補償
- 慰謝料
- 労災保険の給付額を超える休業損害や葬祭料
- 車の修理費用
など